循環器内科で診る症状
循環器内科で診る症状
循環器内科は、心臓や血管を専門とする診療科です。胸痛、背部痛、動悸、息切れ、呼吸苦、足のむくみ、意識が遠のく、失神、歩行時の下肢の痛み、などの症状がある方の診察を行います(高血圧については、生活習慣病のページをご覧ください)。
当院では、心電図、エコー検査(心臓、腹部、下肢静脈)、血圧・脈波検査(血管年齢)、24時間心電図(ホルター心電図)、レントゲン検査(胸部、腹部)、院内迅速検査(BNP、Dダイマー、血球数測定、臓器機能、尿検査、糖尿病)等の各種検査機器を備えており、様々な症状に対する精査を行うことが可能です。当院で実施可能な検査については、循環器内科の検査のページもご覧ください。
胸部には心臓や肺、大動脈など、数多くの重要な臓器が存在します。そのため、胸痛を自覚した患者様の多くは、ご自身が生命に関わる重篤な病気に罹っていることを心配して医療機関を受診されます。当院では以下のような手順により、胸痛を訴える患者様の診療を行います(患者様のご年齢や症状、状態などによって、診療内容が異なることもあります)。
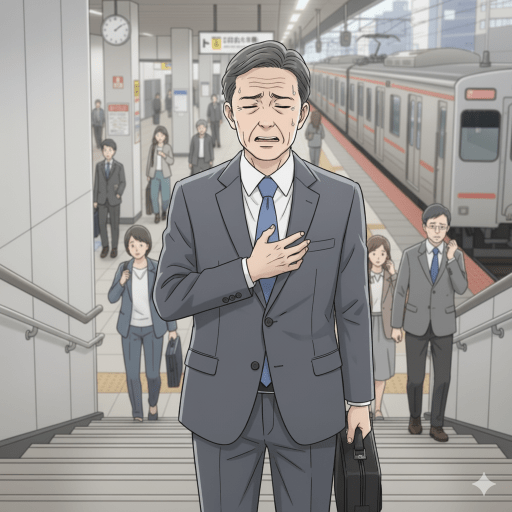
胸痛を生じる疾患は数多くあるものの、一刻一秒を争って緊急に治療を行う必要がある疾患の種類は限られます。特に代表的なものは、急性心筋梗塞、不安定狭心症、緊張性気胸、肺塞栓症、急性大動脈解離などであり、来院時にも強い胸痛が持続している方に対しては、まずはこれらの疾患の有無を判断することから診察を開始します。それぞれの疾患に特徴的な症状を見極めつつ、身体診察や各種院内検査(採血・心電図・レントゲン・心エコー等)を行うことにより、迅速かつ的確な診断に努めます。緊急疾患の可能性が疑われた段階で、速やかに高次救急医療機関への紹介・救急搬送などを手配します。
これらの病気は治療までの時間との勝負です。過去に経験したことのない、強い胸痛を自覚したときは、是非、患者様ご自身の判断で救急車を呼んで下さい。
続いて、緊急性はなくとも適切な治療を要する臓器疾患の評価を行います。具体的には、労作性狭心症や冠攣縮性狭心症、心膜炎・心筋炎、肺炎、逆流性食道炎などがそれにあたります。症状や身体所見、各種基本検査によりある程度の見当を付けた上で、必要に応じて各種精密検査をご案内します。当院では実施できない検査(心臓カテーテル検査、トレッドミル負荷心電図検査、CT、内視鏡検査等)が必要な場合には、適切な連携医療機関に御紹介致します。
皮膚、筋肉、神経、骨・軟骨など、体の表面に近い組織に生じる痛みのことを体性痛と言います。代表的な疾患としては肋間神経痛があります。比較的狭い範囲に鋭い痛みを生じ、姿勢変化や体動、呼吸等により症状の程度が変化することなどが特徴です。殆どの体性痛は、健康や生命を脅かすことはありませんが、診断にあたっては胸部臓器(心臓や肺など)の疾患を除外することが求められます。30歳台までの患者様が胸痛を訴える場合、その原因は体性痛である頻度が高いです。鎮痛薬などによる対処療法を行うことが一般的です。
体性痛の中でも注意が必要なのは、帯状疱疹です。神経痛の出現から数日遅れて、皮膚に多数の小さな発疹が出現します。そのため、発疹が出現する前に受診された場合には、帯状疱疹と診断することが難しい場合があります。治療開始が遅れると全身性の症状が出現したり、後遺症(帯状疱疹後神経痛)のリスクが高まるため、帯状疱疹を疑う発疹が出現した際には、繰り返し受診して頂く必要があります。
「背中が痛い」という症状は、ありふれたものであると同時に、時に命に関わる重大な病気のサインである可能性もあり、注意深い対応が必要です。多くの場合は、肩こりや筋肉痛などのありふれた原因による症状ですが、内臓、特に心臓や大血管、消化器系の病気が原因で背中に痛みを感じることも少なくありません。当院では、問診と診察、各種検査を通じて、その痛みが緊急性のあるものか、あるいは整形外科的な治療が望ましいものかなどを的確に判断し、適切な診療に繋げていきます。
背部痛を訴える患者様の診察で最も重要なことは、まず命に関わる緊急疾患を見逃さないことです。特に、以下のような特徴を持つ痛みは注意が必要です。
突然発症の、引き裂かれるような激しい痛み: 主に肩甲骨の間に痛みを感じる場合、急性大動脈解離の可能性があります。これは、心臓から全身へ血液を送る大動脈の壁が裂ける病気で、一刻を争う緊急手術が必要です。
胸の痛みや圧迫感を伴う背部痛: 心臓の血管が詰まる急性心筋梗塞では、痛みが背中や肩に広がることがあります。冷や汗や息苦しさを伴う場合は特に危険なサインです。
みぞおちの痛みや吐き気を伴う背部痛: 胃や十二指腸に穴が開く消化管穿孔や、膵臓に強い炎症が起こる急性膵炎の可能性があります。
これらの疾患が少しでも疑われる場合は、ただちに連携する高度医療機関へ救急搬送を手配します。また、これまでに経験したことのないような激しい背部痛を感じた際は、迷わず救急車を要請することが大切です。
緊急性は高くないものの、適切な治療が必要な内臓の病気でも背部痛は起こります。
消化器系の疾患: 逆流性食道炎や胃潰瘍では、背中の上部に鈍い痛みを感じることがあります。また、胆嚢に石ができる胆石症では、それぞれ右の肩甲骨下あたりに痛みを感じることがあります。
泌尿器系の疾患: 尿路結石や、腎臓の感染症である腎盂腎炎では、腰に近い背中の痛みが特徴です。
婦人科系の疾患: 女性の場合、子宮や卵巣の病気が原因で背中の下部や腰に痛みを感じることがあります。
当院では、採血や尿検査、心電図、レントゲン、エコー検査などを行うことで、これらの内臓疾患が隠れていないかを慎重に評価します。
背部痛の原因として最も多いのが、筋肉の緊張や骨格の歪みによるものです。他にも、帯状疱疹などの疾患は見逃すことができません。
筋・筋膜性疼痛症候群: いわゆる「凝り」や「筋違い」で、長時間同じ姿勢を続けること(デスクワークなど)や、運動不足、ストレスによる筋肉の過緊張が原因です。
変形性脊椎症・椎間板ヘルニア: 加齢により背骨(脊椎)が変形したり、骨と骨の間にあるクッション(椎間板)が飛び出したりして、神経を圧迫し痛みを引き起こします。
帯状疱疹: 体の片側の神経に沿ってピリピリとした痛みが出現し、数日後に赤い発疹と水ぶくれが現れます。皮膚症状より痛みが先行するため、初期の診断が難しいことがあります。
整形外科的な疾患が強く疑われる場合は、鎮痛薬の処方など初期対応を行うとともに、専門である整形外科やペインクリニックへの受診をご案内いたします。
動悸は、診察が難しい症状の一つです。その理由として、症状の原因が多岐にわたることや、症状があるときの心電図を記録しないと正確に診断できないこと、などが挙げられます。動悸そのものはさほど稀ではない症状ながら、患者様自身に生じると、健康や生命に対する強い不安を掻き立てられるものです。動悸発作を繰り返しているにもかかわらず、医療機関を受診する頃には症状が治まってしまうため、いつまでも診断が付かずに困っている患者様も珍しくありません。
当院では、詳細な問診や診察、および検査を通じて、動悸症状の原因のみならず、心臓の機能や状態の把握にも努めます。これにより、症状の原因となる病態の重症度を、受診された当日のうちに可能な限り見定め、緊急性が高いと判断された場合には高次医療機関への紹介を含めた適切な対応を行います。また、症状の原因となっている臓器(=心臓)の状態を出来るだけ詳しくご説明することで、患者様の不安の軽減にも心掛けます。
健康な心臓では、自律神経(交感神経と副交感神経)の影響を受けて常に心拍数が変動しています。就寝中には副交感神経が優位となって脈がゆっくりになりますし、運動中は交感神経が活性化して生理的な頻脈となります。この生理的頻脈のことを、「洞頻脈」と言います。
運動以外で洞頻脈を生じる原因の代表は、情動(不安・緊張・興奮など)や精神的ストレス、過労、睡眠不足です。心身への過負荷は自律神経の働きに大きな乱れを生じ、動悸症状につながることが珍しくありません。また、発熱、脱水、貧血、甲状腺機能亢進症(バセドウ病)、心不全などの疾患・病態でも洞頻脈を生じえます。若い方(特に女性)では、バセドウ病や貧血が原因となっているケースがあり、ご高齢の方では脱水や心不全などが問題となります。あらゆる年齢層において、正確かつ慎重な評価が必要です。
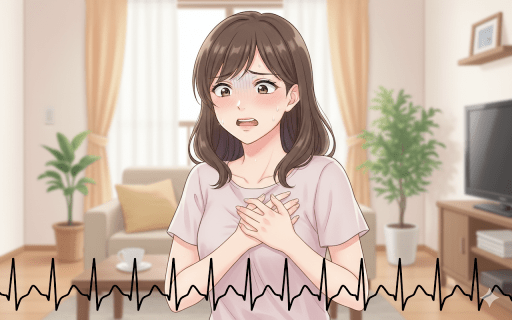
不整脈にはさまざまな種類があり、それぞれに特徴的な症状があります。「脈が飛ぶ感じ」、「心臓がしゃっくりを打つ感じ」、「脈が急に速くなって、急に元に戻る」、「脈の間隔が不揃いになる」、「動悸とともに目の前が暗くなる」、「動悸と胸痛・呼吸苦を同時に自覚する」などの症状は、不整脈が原因となっている可能性があります。
当院では、各種院内検査(採血・心電図・レントゲン・心エコー、ホルター心電図など)により、症状の原因となっている不整脈の的確な診断に努めるとともに、必要かつ適切な治療法をご提案します。不整脈の治療は薬とカテーテル手術(カテーテルアブレーション)の2本立てであり、どちらを選択するかは、症状の強さや、不整脈が健康に与える影響、および患者様のご希望などから総合的に判断します。カテーテルアブレーションが必要な患者様は、速やかに適切な医療機関にご紹介します。
「夕方になると靴がきつくなる」、「指輪が抜けにくい」、「靴下の跡がくっきり残る」といった症状は、「浮腫(ふしゅ)」、いわゆる「むくみ」のサインです。むくみは、多くの方が経験するありふれた症状ですが、その背景には体からの重要なメッセージが隠れていることがあります。特に、これまで見たことのないほどのむくみが出現したり、急に症状が強くなった場合には注意が必要です。当院では、むくみの原因が、心配のいらない生理的なものなのか、あるいは治療が必要な病気によるものなのかを的確に診断し、患者様の不安に寄り添った診療を心がけます。
私たちの体では、血管から組織へ水分がしみ出し、リンパ管などを通って再び血管へ戻るという水分の循環が常に行われています。長時間の立ち仕事やデスクワーク、塩分の多い食事、アルコールの摂取、女性の場合は月経周期などが原因で、この水分のバランスが一時的に崩れると、一過性のむくみが生じます。特に、重力の影響を受けやすい足(下腿)に症状が出やすいのが特徴です。これらは生理的な変化であり、一晩眠ったり、マッサージをしたり、生活習慣を見直したりすることで改善することがほとんどです。
むくみは、心臓、腎臓、肝臓などの重要な臓器の機能が低下しているサインとして現れることがあります。これらの病気によるむくみは、放置すると生命に関わることもあるため、早期の診断と治療が重要です。
代表的な原因疾患としては、心臓のポンプ機能が低下する心不全(息切れや横になると苦しいなどの症状を伴う)、尿として余分な水分や塩分を排泄できなくなる腎不全、血液中のタンパク質(アルブミン)が作れなくなる肝硬変、甲状腺の働きが低下する甲状腺機能低下症、足の静脈に血の塊(血栓)が詰まる深部静脈血栓症(片足だけが急にむくんで痛むのが特徴)、皮膚の感染症である蜂窩織炎などがあります。
当院では、詳細な問診と身体診察に加え、各種院内検査(D-dimerを含やBNPを含む採血・尿検査・心電図・レントゲン・心エコー・下肢静脈エコー等)を駆使し、むくみの原因を慎重に鑑別します。原因に応じた適切な治療を行うとともに、必要であれば専門医療機関と迅速に連携いたします。
「階段を上ると息が切れる」、「以前より歩くペースが落ちた」、「家族や友人の歩くスピードについていけない」、「着替えなどの些細な動作でも息が上がる」。このような「息切れ(呼吸困難感)」は、年齢のせいだと見過ごされがちですが、心臓や肺の病気が原因で生じている可能性があります。息切れは、体が酸素不足に陥っていることを知らせる危険信号です。当院では、息切れの原因を丁寧に探り、患者様が再び快適な日常生活を送れるよう、最適な診断と治療を提供することを目指します。
心臓は、全身に血液を送り出すポンプの役割を担っています。このポンプ機能が低下する心不全という状態になると、肺に血液がうっ滞し(肺うっ血)、効率的なガス交換ができなくなり、息切れが生じます。特に、運動時に症状が悪化する、横になると苦しくて座りたくなる(起坐呼吸)、夜中に息苦しくて目が覚める、といった症状は心不全に特徴的です。その他、狭心症や心筋梗塞、不整脈なども息切れの原因となります。心臓が原因の息切れは、命に関わる状態に繋がりかねないため、早期の対応が重要です。
肺は、空気中から酸素を取り込み、二酸化炭素を排出するガス交換の場です。この機能が障害されると息切れが生じます。代表的な疾患として、気管支が狭くなる気管支喘息や、主に喫煙が原因で肺が壊れていく慢性閉塞性肺疾患(COPD)、肺に炎症が起こる肺炎、肺の組織が硬くなる間質性肺炎などがあります。また、肺の血管に血栓が詰まる肺塞栓症では、突然の胸痛と息切れが出現します。
心臓や肺以外にも、血液中の酸素を運ぶヘモグロビンが減少する貧血や、甲状腺ホルモンが過剰になる甲状腺機能亢進症、精神的なストレスや不安によって呼吸が速くなる過換気症候群など、息切れの原因は多岐にわたります。
当院では、問診や身体診察に加え、院内検査(採血・心電図・レントゲン・心エコー、呼吸機能検査等)を組み合わせることで、息切れの根本原因を迅速に診断します。原因を特定し、適切な治療を開始することで、息切れ症状の改善を目指します。年のせいと諦めずに、ぜひ一度ご相談ください。
「失神」とは、一時的に脳への血流が低下することにより、短時間(通常は数十秒から数分以内)意識を失う発作のことです。「目の前が暗くなる」「気が遠くなる」といった前触れを感じることもあれば、何の前触れもなく突然意識を失うこともあります。失神は、ご本人が意識を失うことへの恐怖を感じるだけでなく、転倒による大怪我のリスクも伴います。また、その背景には命に関わる重大な病気が隠れている可能性もあり、決して軽視できない症状です。当院では、失神の原因を明らかにし、再発を予防するための適切な診断・治療・生活指導を行います。
失神の中で最も頻度が高いのが、自律神経の反射的な反応によって起こる「反射性失神」です。長時間の立位、痛み、精神的なストレスや恐怖、特定の状況(排尿・排便・咳など)が引き金となり、自律神経のバランスが崩れ、急激な血圧低下や心拍数の低下をきたして意識を失います。一般に「脳貧血」と呼ばれる状態がこれにあたります。命に関わることは稀ですが、再発しやすいため、どのような状況で起こりやすいかを把握し、それを避けるような生活上の工夫が重要となります。
急に立ち上がった際に、血圧が維持できずに脳の血流が低下して起こる失神です。脱水状態や、特定の降圧薬・利尿薬、自律神経の病気などが原因となります。特にご高齢の方では、脱水や薬剤が原因となっていることが多く、原因に応じた対策が必要です。
最も注意が必要なのが、心臓の病気が原因で起こる失神です。これは突然死に繋がる可能性がある危険なサインです。原因としては、脈が極端に遅くなる徐脈性不整脈(洞不全症候群や房室ブロックなど)や、極端に速くなる頻脈性不整脈(心室頻拍や心室細動など)があります。また、心臓の出口が狭くなる大動脈弁狭窄症や、心臓の筋肉が厚くなる肥大型心筋症なども、運動時などに失神を引き起こすことがあります。
心原性失神は前触れなく突然起こることが多く、横になっている時や座っている時にも起こりえます。当院では、失神を経験された患者様に対して、心電図やホルター心電図、心エコーなどの検査を行い、危険な心臓病が隠れていないかを重点的に評価します。心原性失神が疑われる場合は、ペースメーカー治療やカテーテルアブレーションなど、専門的な治療が必要となるため、速やかに高度医療機関へご紹介いたします。
当院ではセカンドオピニオン診療を行っておりません。また、すでに他の医療機関にて治療中の心疾患について、当院での相談を希望される際には必ず紹介状をお持ち頂きますよう、お願い致します。かかりつけの先生からの紹介状を持たず受診をされると、過去の経緯や検査結果などがまったくわからないところから手探りの診察となるため、当院にて正確な診断・治療を行うことは、却って困難になります。また、検査や治療が重複することにより、金銭面のみならず、患者様の身体面でも大きな負担が生じます。さらに健康保険側では、医療費の適正化の取り組みとして重複受診を行っている方の調査を行っており、患者様に個別に連絡が入るケースがあります。ご理解、ご協力のほど、なにとぞよろしくお願い申し上げます。